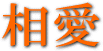『』はイタリア語です。
広いリビングにいる高塚友春(たかつか ともはる)はじっと時計を見つめた。
重厚で、歴史のある屋敷に相応しい大きな置時計の針は、そろそろ午後四時を回りそうだ。
「・・・・・何しよう・・・・・」
ふうと大きな溜め息をついたが、頭の中には何も思い浮かばない。
まだ、彼がいたら話も出来るし、出掛けたいと一言伝えることも出来たと思うが、今朝から仕事に出掛けた彼はその間際
に、朝にするには深く友春の口腔を貪った後、くったりと力が抜けた身体を抱き寄せて言ったのだ。
「私が帰るまでおとなしく待っているんだ。いいな?」
その言葉に、友春は逆らうつもりもなくて屋敷の中にずっといた。
しばらくは執事の香田夏也(こうだ なつや)が時折姿を現して相手をしてくれたが、一時間ほど前、珍しく慌てた様子で
やってきたかと思うと、
「大変申し訳ありません。急用で少し出掛けなければならなくなりました」
この屋敷の中で一番忙しい香田を引きとめておくことなど出来なくて、友春は1人で大丈夫だと告げたが、彼がいなく
なると今度こそ寂しくてたまらなくなる。
「・・・・・あ〜あ」
友春はまた溜め息をついた。
イタリアでも有数の資産家であり、裏の顔はイタリアマフィアの首領、アレッシオ・ケイ・カッサーノ。
紆余曲折の末、友春自身がアレッシオの手を取ってイタリアに渡って7ケ月。しかし、友春は少しだけ後悔をしていた。
それは、自分がイタリアで何をするのか、何も決めていなかったことだ。大学まで出してもらって無職とは両親にも申し訳
ないし、生活のすべてをアレッシオに面倒を見てもらうというのも気が引けた。
そのことをアレッシオに訴え、バイトでもなんでも少しお金を入れたいと訴えたが、
「恋人のすべての面倒をみるのは当たり前のことだろう」
と却下され、その夜はしつこく泣かされた。
友春も、アレッシオが想像出来るはるか上の財力を持っていて、自分1人の面倒くらい簡単に見れるだろうというのはわ
かっているつもりだ。それでも、アレッシオと多少なりとも対等な位置にいたいと願う気持ちは消えないし、日々屋敷の中
で多くの時間を過ごすのは居たたまれない。
イタリアに来てひと月ほど経った時、友春は一度屋敷から徒歩で一時間余りの場所の小さなパン屋にバイトに行くこと
にした。
片言のイタリア語しか話せなかったが、店の主人は気の良い初老の男で、異国の地で頑張りなさいと言ってくれたのだ
が。
バイトを始めた二日後、入口の鐘の音に顔を上げた友春は、そこに立っていた店には不釣り合いの上等なスーツを着
た端正な男の顔を見て青ざめてしまった。
「逃げ出す資金でも稼ぐ気か?」
違うと、何度訴えても許してもらえなかった。
アレッシオはおろか香田にさえも秘密にしていたことが不味かったらしく、それから三日間は寝室からも出してもらえず、さ
らにひと月以上、アレッシオと共にする外出以外はすべて禁止にされてしまった。
愛されているとは思う。
しかし、その愛は受け止めるのにはあまりにも重く、一方的で、友春はやっと男に感じ始めた自身の愛情さえ疑問に思っ
てしまいそうだった。
今では怒りも解け、香田と共になら外出も許してくれるようになったが、友春はこのままでいいのだろうかと日々真剣に
悩んでいた。
「・・・・・本でも読もうかな」
自分自身に言い聞かせるようにして友春は立ち上がる。
屋敷にいる大半の時間を過ごす、まるで図書館のように多くの蔵書がある屋敷の書庫は、友春にとってとても居心地の
いい場所だった。
大きく、重い扉を開けた。古い、木製で出来た扉が少しも軋んだ音を立てないのは手入れが行きとどいているからだ。
何冊あるかわからない本も1冊1冊埃を被っておらず、友春はアレッシオがこういうところにまで目を配っているということに
驚くと同時に、古いものも大切にしている姿勢を好ましく思っていた。
「これ、全部見終えるのってどのくらい掛かるだろう・・・・・」
イタリア語はまだほんの少しかじっただけだし、英語も不自由なく操れるというわけでもないので、友春が好んでみるのは
もっぱら写真集だ。
風景が多いそれは各国様々なものがあり、まるで見ているだけで世界旅行をしている気分になれた。
先日、それらの中に日本の桜だけを写したものを見つけ、後の楽しみと取っておいたが、少し気分が落ち込んでしまっ
た今は懐かしい風景を見て気持ちを浮上させたいと思った。
「え・・・・・っと」
(確か、あっちのコーナーに・・・・・)
写真集だけでも数百冊あった一角に足を向けた友春は、
「!」
そこに、見知らぬ人影を見て思わず足を止めてしまった。
(だ、誰・・・・・?)
屋敷に勤めている人たちの顔と名前は、さすがにこの数カ月で覚えていたので、目の前の人物がその誰とも違うというの
はさすがにわかる。
四十代半ばだろうか、ノーネクタイのジャケット姿だが、アレッシオがよく着ているスーツのように仕立てが良いというのは
一目見てわかり、、細いフレームの眼鏡を掛けて、鼻の下には髭を蓄えていた。
身長はあるが全体的に線が細く、理知的な風貌をしたその男はゆっくりと顔を上げると、目が合った友春の姿に驚く様
子を見せることなく、目を細めて笑みを浮かべた。
「Dolcetto o Scherzetto?」
「・・・・・え?」
(ドルチェット・オ・・・・・?)
甘い声で流暢に流れ出た言葉の意味は友春にはわからなかった。
普通の会話なら出来るはずなのにそれだけで焦ってしまい、あのという日本語しか口から出てこない。
「・・・・・」
「あ、あの、ごめんなさい・・・・・ス、Scusi・・・・・?」
香田から習った言葉のチョイスや発音が合っているのかどうか自信がないままに口にすると、目の前の男はさらに笑みを
深めて優雅な仕草で軽く会釈した。
「Si figuri」
「・・・・・」
どうやら相手が怒っていないらしいことに友春は安堵して、改めてどうしてこんなところに見知らぬ男がいるのかということ
を考える。アレッシオも香田も今は屋敷にはいないが、他の者だって十二分に屋敷を守る力がある。
侵入者をやすやすと許すわけがないと思うと、やはりこの男はアレッシオの関係者なのだろうか?
「・・・・・Come si chiama, Lei? 」
「Ferdinando」
「フェルディ、ナンド?・・・・・あ」
ふと、友春は彼が手にしていたものが目に入って思わず声を上げた。それはついさっきまで自分が見ようと思っていた日
本の桜の写真集だと気付いたからだ。
男・・・・・フェルディナンドは直ぐに友春の視線に気付いたようで、手に持つそれを軽く上げて話しかけてきた。
「君も読むつもりだった?」
「はい・・・・・え?今、日本語・・・・・」
「ああ、すまない。君があまりにも必死で話してくれたから、つい私も意地悪をしてしまった」
「・・・・・」
フェルディナンドの流暢な日本語に、友春はどう反応していいのかわからなかった。アクセントも、チョイスも、日本人とほと
んど変わらないそれはまるでアレッシオのように完璧だ。
どうしてという疑問と共に、友春はふとあることを思い付いた。
「あ、あなたは・・・・・」
「トモ!」
その時、静かな書庫の空気を鋭く斬り裂くような声が響いた。
「トモッ」
驚くあまり直ぐに返答が出来ないでいると、続いて苛立ったように名前を呼ばれる。
「こ、こっちです」
友春が慌てて応えると、直ぐに見慣れた男の姿が現れた。
「ケ、ケイ」
アレッシオは友春の側まで歩み寄ると直ぐに肩を抱き寄せた。人前だということに友春は一瞬逃げようとしたが、アレッシ
オはそんな動きを許してはくれず、さらに手に力を込めて目の前の男を睨みつけている。
「ケイ、この人って・・・・・」
『どうしてあなたがここにいるんです』
『明日は Tutti i santi だろう?墓参りに行く前にそちらによると連絡をしたと思うが?』
『・・・・・ええ、一時間ほど前に聞きました』
『相変わらずナツは有能だな』
怒ったように話すアレッシオの口調は早口でなかなか友春はその意味を理解出来なかった。しかし、2人の会話を邪魔
してはならないとじっとおとなしくしていたが、そんな友春にフェルディナンドが悪戯っぽく笑いながら声を掛けてきた。
「驚かせて悪かったね、トモ。ケイがいない時に君と話してみたかったから。どんな子かなと思っていたけど、素直で可憐
なたたずまいが気にいったよ」
「あ、あの」
「紹介が遅れたが・・・・・私はフェルディナンド・ロイ・カッサーノ。ケイの父親だ」
「ケ、ケイのっ?」
まさかと思っていたことが本当だったことに友春は絶句してしまう。
(本当に、ケイのお父さんなんて・・・・・)
写真も見せてもらっていなかったアレッシオの両親。
元マフィアのドンで、自分の妻でさえも放逐し、厳しい血の掟を守ってきたらしいというのは香田の前の執事から聞かされ
ていたし、妻がいるというのにアレッシオの母親と優雅な世界旅行に行っていると聞けば、随分豪胆で精力的な人だろう
と想像していた。
しかし、今目の前にいるフェルディナンドはとてもアレッシオのような子供がいるとは思えないほど若々しく、線が細くて穏
やかな雰囲気だった。まさか、マフィアのドンだったとは思えず、友春は何度も2人の顔を交互に見つめる。
そんな友春の素直な反応にアレッシオも怒りを持続出来なかったのか、やがて大きな溜め息をつくとまとっていた厳しい
空気を弛めた。
『フェルディナンド様が屋敷に来られるそうです』
香田から掛かってきた電話に、アレッシオは驚きというよりもやられたと舌をうった。
以前からアレッシオが側に置く友春に会いたいと言ってきていたが、日本贔屓の父親に会わせると絶対に気にいることは
わかっていたのでずるずると先延ばしにしていたのだ。
しかし、どうやらそんなアレッシオの対応に痺れを切らしたのか、いきなり旅行先から戻ってきてしまったらしい。イタリア
では皆が知る諸聖人の日というのを利用したのだ。
キリスト教の祝日の一つだが、イタリアではこの日に墓参りをする者も多い。アレッシオももちろん先祖の墓を参るつもり
だったが、今回は友春も連れてと考えていた。
その前に、今日のハロウィンに友春を驚かせようと色々と考えていたのだが、それもすべて父の出現で流れてしまった。
『母さんは一緒じゃなかったんですか?』
『今頃はナツが相手をしてくれているよ。・・・・・ところで、ケイ、日本語で話した方がいいんじゃないか?』
日本人の母とのコミュニケーションを図るために、完璧に日本語をマスターした父。友春のために日本語を習得した自分
と重なって、なんだか・・・・・面白くない。
「トモ」
しかし、そんな余裕のないところを友春に見せたくなくて、アレッシオは興味津々な眼差しを向けてくる友春に言った。
「明日の墓参りに戻ってきたらしい」
「墓参り?」
「11月1日は Tutti i Santi (トゥッティ イ サンティ)といって、聖人の死を悼み、神の恩恵に感謝するという日なんだ。こ
の日に合わせて墓参りをするイタリア人は多い。私も明日、お前を連れていくつもりだったんだが」
「・・・・・そんな大事な日に、僕も一緒に行っていい、の?」
心配そうに聞いてきた友春に、アレッシオは当然だろうと言いきる。
「トモは私の伴侶だろう?」
「ケ、ケイッ」
どうやら友春は父の存在を気にしているようだが、今の屋敷の主人は自分で、組織の頂点に立っているのも同様だ。
誰も意見など出来ない。
それは父自身もわかっているはずだと視線を向ければ、父は面白そうに口元を緩めた。
「・・・・・」
(何を楽しんでいるんだ)
父がまだ《ドン・カッサーノ》と呼ばれていた時代、カッサーノ家の頂点に立つ父は優美で優しげな外見とはまるで違う、
冷酷で冷淡な男だった。
力を好み、血を好み・・・・・自身を裏切った妻の許しを乞う声もまったく聞こえないかのように放逐し、直ぐに新しい妻を
迎えた父。人としての情などないとまで言われた父が突然変わったのは、アレッシオが正式に後継ぎとして表に立った
時だったように思う。
その地位を降りた父は直ぐに妻を実家に帰すと、愛人であった母を連れて世界中を旅し始めた。
年に数回掛かってくる電話の声は驚くほど穏やかになっていて、まるで人が違う。父がなぜ変わったかという理由を知ろう
とは思わないが、母が今のまま幸せに笑っていてくれたらいいとだけ思った。
「ケイ、Dolcetto o Scherzetto?」
フェルディナンドが唐突にアレッシオに言った。アレッシオは不機嫌そうに、ありませんと答える。
さっきもわからなかった言葉の意味を、友春はアレッシオに訊ねた。
「今のって、なんて?」
「Dolcetto o Scherzetto のことか?ハロウィンの Trick or Treat をイタリアではこう言うんだ」
「ああ・・・・・そうなんだ」
ようやく納得した友春に、フェルディナンドは声を出して笑った。
「驚かせて悪かったね。でも、君が菓子を持っていないから少しからかったんだ。ケイ、君も同じだよ?」
「・・・・・母さんより先に、あなたにトモを会わせるつもりはなかったんですが」
「そう言うと思った。だからナツを呼び出して屋敷を空けさせたんだが、まさかこんなにも早く君が帰ってくるとは思わなかっ
た。それほどにこの子が大切だということか」
「当り前だ。たとえあなたが一族のためにトモと別れろと言ったとしても、私はトモを離さない。一族がトモを受け入れない
のなら、私の方から一族を捨てます」
「ケ、ケイ・・・・・」
まさかそこまでアレッシオが考えていたとは思わず、友春は絶句してしまった。次の瞬間には頬が熱くなり、なんだかまとも
にアレッシオの顔を見ることが出来なくなる。
自分が思っている以上にアレッシオに愛されている・・・・・それを、こんなふうに父親の前ではっきりと言いきってくれる彼
の強さが羨ましく、嬉しかった。
「私は、反対する気はないよ」
そんな友春とアレッシオを交互に見つめたフェルディナンドは、そう穏やかに口にする。
「愛する人と引き離される悲しみを、我が子に味あわせたいと思う親などいない。・・・・・トモ」
「は、はいっ」
「もう直ぐ私のユーリがやってくる。きっと君と気が合うだろうな」
「ユーリ、さん」
「母の名前は百合子(ゆりこ)と言うんだ。・・・・・何時までも新婚気分に浸らずに、一族の仕事を手伝ってください。子
供の手助けをするのも親の役割だと思いますが」
「楽隠居をさせてくれるのも子供の甲斐性だよ」
「・・・・・」
(な、なんだか・・・・・)
フェルディナンドと言い合いをしているアレッシオは、何時もの彼とは違って酷く子供っぽく見えた。そう言ったら彼は心外だ
と否定するかもしれないが、友春の目には父親に甘えているように感じるのだ。
それに、フェルディナンドがちゃんとアレッシオのことやその母親のことを思っているというのもわかった。複雑な家族だが、
そこには確かな愛情があるのだ。
トントン
その時、ノックの音がした。そして、扉が開く音がする。
「アレッシオ様、奥様が・・・・・」
「ロイ、ケイ、ここにいるの?」
香田の声にかぶせるようにして、優しく軽やかな声がした。
「ユーリ、ここだよ。ケイも、ケイの大切なトモもここにいる。・・・・・トモ、菓子を持っていないと、きっとユーリに悪戯をされ
るよ。彼女は楽しいことが好きだから」
「えっ?」
笑いながらアレッシオの母親を迎えに行くフェルディナンドの背中を見つめた友春は、唐突にアレッシオに手を握られた。
「ケイ?」
「あの人のいいなりになるのは面白くない。これを渡すんだ、驚く顔が見れるかもしれない」
コートのポケットから取り出された数個の飴玉を見つめ、友春は改めてアレッシオの顔を仰ぎ見る。その顔が不敵に笑ん
でいるのを見て、友春もなんだかおかしくなった。
今日はハロウィン。少々の悪戯なら許されるはずだ。
(ケイと一緒なら・・・・・大丈夫)
側には、味方になってくれる彼がいる。
そして、このアレッシオと、あのフェルディナンドが大切に思っている人なら、きっと友春も好きになれる。
「・・・・・」
近づいてくる二つの靴音を聞きながら、友春は手の中の飴玉を握り締めた。
「・・・・・トモ?」
「は、初めまして、僕は・・・・・」
でも、この飴玉はきっと・・・・・使わない。
end
かなり遅れてしまいましたがハロウィンの話。
早く彼らのイタリアでの生活も書きたい〜っ。