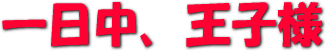西原真琴、22歳のお誕生日編。
レモンの良い香りがする。
「ん・・・・・」
真琴はそれに誘われるように寝返りをうった。
(なんだろ・・・・・こ、れ・・・・・)
和食党の海藤が作ってくれる朝食はほとんど日本食で、毎朝香るのは味噌汁の匂いだ。それが、どうしてこんなレモンの香り
がするのかと考えた真琴は、
「・・・・・あ」
ぱちっと、目を開いた。
「お目覚めですか、王子様」
「・・・・・え?」
その視界に映ったのは、綺麗で、大好きな人の顔。
普段はほとんど表情の変わらないその顔が、自分に対してだけ何時も優しく緩んでいることは自覚していたが、今日の笑顔は
とびきり甘い気がした。
「・・・・・か、どー、さん?」
「誕生日、おめでとうございます」
「あ・・・・・っ」
その言葉に思わず目を見張った真琴が何かを言い掛ける前に、海藤の綺麗な顔が近付いて来て・・・・・そのままチュッと軽く
唇が触れてきた。
数日前、夕食を済ませた後に一緒に食器を洗いながら海藤が言った。
「誕生日プレゼントは何が良い?」
その言葉に真琴は改めてカレンダーを見、自然に緩んでしまう頬を慌てて押さえた。
プレゼントを貰うということ自体も子供のように嬉しいと思うが、それ以上に毎年こうして海藤と誕生日を過ごすことが出来て嬉
しい。
誕生日に限らず、海藤には何時も分不相応なほどの贈り物をしてもらっているし、特別何か欲しいというものも無い。
そう思った真琴は、今一番彼にして欲しいことを言ってみることにした。
「あの・・・・・」
「ん?」
「・・・・・一日中、一緒にいたい、です」
その言葉に、海藤は一瞬目を見張り、次の瞬間ふっと目を細める。
その表情の甘やかさに真琴は頬が熱くなってしまい、誤魔化すようにガシガシと皿の泡を流し落とす。
(は、恥ずかしい・・・・・)
一緒に暮らし始めて何年も経つというのに今だ海藤に恋している感じがして、真琴は隣に立つ海藤の体温をますます熱く感
じてしまった。
「真琴」
しばらくして、海藤が名前を呼んでくる。
「は、はい?」
「その日・・・・・23日は、1日、ずっと一緒にいよう」
続いてそう言ってくれ、真琴の声は弾んだ。
「いいんですか?」
「ああ。いや、1日一緒にいるだけじゃなく、その日はお前を王子様のように扱おう」
「え?」
どういうことなのかと真琴は聞き返したが、海藤は自分の思い付きが気に入ったのか楽しそうに笑って楽しみにしろと言う。
(何時だって、大事にしてくれてるんだけど・・・・・)
王子様のようにというのが良く分からなくて、真琴はじっと海藤の横顔を見る。
しかし、海藤が自分に対して悪いことをするわけがないと信じている真琴は素直に頷き、いったいどんなふうにしてくれるのだ
ろうと楽しみにすることにした。
(王子様って、何かの例えだと思ってたけど・・・・・)
海藤の言葉に身体を起こした真琴はそのまま足をベッドから下そうとしたが、
「私がしましょう」
そう言ったかと思うと、海藤の手が腰と膝裏に回り、いわゆるお姫様抱っこをされてしまった。
「か、海藤さんっ?」
「今日は1日、お前は王子様だ。・・・・・いや、王子、今日はなんなりと私に命令して下さい」
「め、命令って・・・・・」
海藤の言葉に嘘は無く、真琴はそのままリビングまで抱かれて運ばれ、そっとソファに下される。
「今日の朝食はマフィンを焼きましたよ。飲み物はレモンティーにしましたがいいでしょうか?」
「あ、は、はいっ」
何だか、海藤に敬語を使われるのは慣れなかった。自分よりも一回り以上年上ということもあるし、何より人間的にというか、
自分が海藤より勝っているとはとても思わないので、冗談でも傅かれるという状態は居心地が悪い。
そんな真琴の心境を知ってか知らずか、海藤自身はこの遊びを気に入っているようで、甲斐甲斐しく真琴の世話を焼いてく
れた。
「・・・・・」
「・・・・・」
今目の前では、海藤がカップに入っているレモンティーに息を吹き掛けて冷ましてくれている。
自分の足元のラグに片膝をつけている海藤の目線はいつもよりずっと下だ。伏せたまつ毛が思いの外長いなと思っていると、
海藤は顔を上げて笑みを向けてきた。
「熱いので気を付けて下さい」
「は、はい」
おずおずとカップを受け取り、一口口を付けた真琴に、今度はマフィンを一口大に千切り、ジャムを塗って口元に差し出された。
「どうぞ」
「あの、自分で・・・・・」
「あなたが手を汚されなくてもいいんですよ」
「海藤さんってば!」
なんだか落ち着かないですと訴えると、海藤は笑って真琴の手からカップを受け取る。
「貴士とお呼び下さい、王子」
「・・・・・っ」
(ぜ、絶対に面白がってる!)
海藤らしくない意地悪だと思うが、きっと海藤は苛めているという意識はないだろう。
(でも、海藤さんが召使いなんて絶対に似合わないって)
緊張のあまり落ち着かない朝食を終えると、海藤の手で着替えをさせられる。
パジャマのボタンを色っぽい意味ではなく外されるのは別の意味で恥ずかしい。真琴は固まったように海藤のなすがままになっ
ていた。
「何かしたいことがありますか?」
「し、したい、こと?」
再びソファに腰を掛けた真琴は、目の前に跪いている海藤をじっと見た。
「何でも言って下さい」
「で、でも・・・・・」
改めてそう言われても、真琴は急には何も思い付かない。
今日は一日海藤と一緒にいられるだけが望みだったので、他に何がしたいかなど全く考えていなかった。
それに、今日は朝から海藤の見慣れない行動に戸惑ってしまって、まだ頭の中が混乱している最中だ。真琴は首を傾げてか
ら横に振った。
「ない、です」
そう、答えるしかない。
「何も?」
「・・・・・はい」
「それは困りましたね」
「え?」
「私のすることがありません」
さほど困ったような物言いではないが、真琴は反射的に頭を下げてしまった。
「あ・・・・・ごめんなさい」
それでも、真琴が思い当る望みというのは全て海藤に関することばかりなので、その海藤にしてもらうことは・・・・・やっぱり無い
のだ。
「では、バースデイケーキを作ってもよろしいですか?」
「ケーキ?手作りしてくれるんですかっ?」
「菓子作りは得意ではありませんが、指南してくれる相手がいたので」
それは、きっと綾辻ではないだろうか。
わざわざ手を掛けてもらうことが申し訳ないと思いつつ、真琴はお願いしますと言った。出来れば手伝わせてもらいたいが、それ
が無理でも作業をしてくれる海藤をじっと見ているのも楽しいと思う。
「では、キッチンに」
そう言いながら立ち上がった海藤のシャツを、真琴は慌てて掴んで引き止めた。
「俺も一緒に行きます!」
「王子も?」
「えっと、見張りで?」
手伝いとは言えないので、王子様らしくそう言ってみた。胸を張らず、少し海藤の反応を窺うような感じになってしまったのでとて
もそうは見えないかもしれないが、海藤は鷹揚に頷くと再びお姫様抱っこをして真琴をキッチンへと連れて行ってくれた。
生クリームの甘い匂いがする。既に生地は用意していたようで、オーブンに入れるだけになっていた。
生クリームを泡立てている海藤の姿は、まるで高貴なパティシエのようだ。
「・・・・・」
(カッコいいなあ・・・・・)
白いシャツに黒いエプロンという格好でも、海藤の美貌は全く遜色ない。いや、むしろ何時もの涼やかな容貌から、撫でつけて
いない休日仕様の髪の海藤は色っぽくて、真琴は顔が赤くなるのを必死で誤魔化していた。
「王子」
「え?」
朝からずっとそう呼ばれているので、いい加減反応するようになっていた。
ぼうっと海藤の後ろ姿に見惚れていた真琴が視線を合わせると、目の前に美味しそうなイチゴが差し出される。
「これ・・・・・」
「味見をお願いします」
「あ、味見ですね」
(俺がしたんじゃ、なんだか摘み食いに見えちゃうけど)
それでも素直に口を開けた真琴に、海藤が大ぶりのイチゴを食べさせてくれた。一口ではとても無理だったので途中で噛むと、
果汁がつっと顎に伝ってしまう。
慌ててそれを拭おうと手を上げた真琴だが、
「そのまま」
その手を海藤に掴まれたかと思うと、海藤の顔が近付いてきた。
(え・・・・・?)
「ひゃっ!」
ペロッと、顎に舌を這わせられる。
「あなたは指一本も動かさなくてもいいんですよ、王子」
「か、海藤さんっ」
目の前の海藤は笑っている。悪戯っぽい笑みを目を丸くして見つめ返していると、今度は唇にキスをされた。
「王子の唇は甘いですね」
「た、食べ物で遊ばないように!」
どちらかといえば、食べ物を介して自分をからかって欲しくなかったのだが、海藤は自分の指に残っている食べ掛けのイチゴを見
下ろして言う。
「それは命令ですか?」
「・・・・・命令ですっ」
「分かりました」
どうやら、真琴の命令に従うのが楽しいらしい。
海藤が笑いながらそのイチゴを再び真琴の口元に差し出してきたので、真琴は今度はわざと指ごと口に含んだ。
元々器用な海藤は、苦手だというケーキ作りも真琴よりも数段上手く、ケーキはたちまち真琴の目の前で形を成していった。
フルーツたっぷりなので時々摘み食いをさせてもらいながら(それも、やっぱり手で食べさせてもらう形になってしまった)、綺麗に
デコレーションされていくケーキを見ていると自然に顔も綻んでしまう。
「美味しそう」
「本当に美味しかったらいいんですけど」
「大丈夫ですよ」
(海藤さんの愛情たっぷり入ってるんだし)
チョコレートホイップで、『まことおうじ たんじょうびおめでとう』と書かれたのは照れ臭いが、これで普通のケーキが一瞬にして
誕生日仕様になるのが楽しい。
「直ぐに食べますか?」
「ん〜・・・・・夜の楽しみに取っておきます」
出来たてを食べるのもいいが、夜に恋人に戻った海藤と食べる方がもっと楽しいと思う。
(・・・・・そっか。そういう命令も出来るんだ)
王子様というのも気恥ずかしいが面白かった。だが、真琴にとっては、恋人の海藤と一緒にいる方が何倍も嬉しいのだ。
命令で、恋人に戻って欲しいと言えば、きっと海藤はその願いを直ぐに叶えてくれるだろうが、そう考えると何だか目の前にいる
召使いになりきっている海藤がとても貴重に見えた。
何時もは己が仕えられる立場の彼が(無茶な命令などしないが)、楽しそうにしているのも可愛くて、真琴は何だかこのまま解
放してしまうのもつまらないなと思ってしまう。
そんな風に思ってしまうというのは、どうやら自分も海藤の作ったこの雰囲気にのまれてしまったのかもしれなかった。
「では、王子、次は何を致しましょうか?」
跪く海藤に、真琴は少し考えて言った。
「隣に座って、話をしましょう」
「話を?」
「色んなこと、いっぱい話したいです。後は、夕食の支度は一緒にして、食べる時は・・・・・恋人に戻ること」
「・・・・・はい」
「命令ですからね?」
「分かりました、王子」
海藤は立ち上がり、そのまま真琴の横に座ってくれる。
後もうしばらくは王子様気分に浸って、自分よりも立派な召使いに奉仕されるのもいいかもしれないと思ってしまったのは・・・・・
海藤には秘密だ。
愛する人の、大切な誕生日。
共に過ごすだけでも幸せなのに、その微笑み一つ、言葉一つに、己の方が癒され、最上の喜びを感じることが出来る。
プレゼントはちゃんと買ってあったが、少し趣向を変えて些細な遊びを真琴に仕掛けてみた。
一日世話をし続けるのも楽しかったが、恋人に戻った瞬間の真琴の嬉しそうな顔がとても心に沁みて、海藤は強くその身体を
抱きしめた。
来年、そしてさらにその次の年と、毎年毎年、共にいる時間を重ねることが出来ればいいと思う。
そのたびに、今日の日を感謝するだろうと思いながら、海藤は改めて愛しい恋人に告げた。
「誕生日、おめでとう」
end
海藤さんに敬語を使わせたくて書いた話(汗)。
真琴が焦るのも無理ないかもしれません。