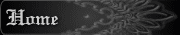赤の王 青の王子
1
※ここでの『』の言葉は日本語です
夜明け前、惑いの森まで遠駆けに来た時、突然の霧が自分を包んだ。
視界がなくなり、馬を降りた時、複数の気配と声に気付いて剣に手をやると、現れたのは奇妙な格好をした数人の男達。
小柄な人影にのしかかる男の気配が不快で、躊躇なく剣を振り下ろした。
切れ味の鋭い剣は簡単に男の腕を切り離したが、戦に慣れているアルティウスは何の感慨もない。
ふと、小柄な人物に視線を向けると、大きな目が張り裂けるほど大きく見開かれ、異様なものを見るような視線をこちらに
向けていた。
そして、一瞬の後、プッツリと糸が切れるように倒れてしまった。
「ここがディーガの言っていた異国・・・・・か」
剣に付いた血糊を軽く振り払うことでとると、アルティウスは見慣れない景色に視線を移した。
砂漠の多い世界の中でも緑が多いと自負していた自分の国だが、目の前に広がっている鮮やかな緑は目に痛いほどで
ここが自分のいた世界ではないと直ぐに分かった。
何の知識もないままこの状態になれば、《赤の狂王》と呼ばれるアルティウスもさすがに戸惑ったかもしれないが、三夜ほど
前、王族専属の占い師が先読みを伝えてきたのだ。
『 近い未来、赤の王は白き異国の者に出会う
その者 王に絶大な力を与えるが
世は戦火の火に包まれるであろう 』
力が全ての源力だと思っているアルティウスにとって、その先読みはまるで根拠のない戯言としか思えなかったが、今目に
しているものを受け入れる許容はもっていた。
「それにしても、この地の者は皆剣を携えずにいるものか・・・・・。力があると思えば泣き叫ぶばかり、我が国の幼子の方が
よほど度量があるというもの」
言葉は分からないものの、威嚇しているだろうという口調は感じ取れたが、目は既に怯えを含んでおり、アルティウスが少し
身じろぎしただけでビクッと身体を縮こまらせていた。
勇猛果敢な自国の民とはかけ離れた弱体ぶりに、これ以上剣を汚す事の方が馬鹿らしい。
アルティウスは気を失っている男達から早々に興味を失うと、少し離れた場所に倒れている男を振り返った。
男・・・・・というより、まだ少年といった方が相応しいか、自国の逞しい女達よりも一回りほど細い身体の少年は、今だ目を
覚ます気配はない。
アルティウスは傍に歩み寄り、跪くとその身体をかかえ上げた。
「軽い」
本当に子供のような体付きだが、その身体は女よりも柔らかく、肌は眩しいほどに白い。
「・・・・・」
整った顔立ちは本当に少女のようで、アルティウスは急に喉の奥が渇いてくるのを感じた。
26歳のアルティウスは、皇子3人、皇女2人をもうけ、跡継ぎを作る義務は果たしたと、今は女よりも政治の方に興味
が移っているが、王という立場上、献上される女の数は限りがなく、まるで日替わりのように寝所にあがってきていた。
ほとんどの者が一度だけの機会しかなかったが、若く、美しく、強く、何より絶大な権力を持つアルティウスの寵愛を得ようと
する者は途切れることはなかった。
アルティウスにとって肉体の交わりは、単に生殖行為か、欲求の解消に過ぎない。
そんな、どこか冷めていたアルティウスの欲情が、今目の前の少年に対してなぜか沸き上がって来た。
欲しい・・・・・自然とそう思う。
そして、欲しいものは自分で奪うもの・・・・・そう教えられたアルティウスに迷うことはなかった。
「もう、ディーガが呼ぶ頃か」
惑いの森から姿を隠した王を捜す為、優秀な臣下達はすぐさま様々な手を打っているだろう。
異国に呼ばれた王を呼び出す術はディーガしか知らず、そのディーガを王宮まで連れて来る時間を考えると、そろそろこの
地を離れる時間だろう。
アルティウスは、今だ自分の腕の中で意識のない少年の顔を見つめた。
「私に欲されることを名誉に思え」
【王、赤の狂王よ】
ディーガの声が聞こえた。
「ディーガ、このまま召還せよ」
【御意】
返事とともに、辺りが再び霧に包まれる。
再びこの地に立つことが出来ると限らないが、このまま少年を連れ去ることに何の躊躇もない。
「連れて行くぞ、我が王国に」
やがて深い霧が晴れた時、二人の姿は忽然と消えていた。