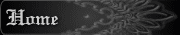赤の王 青の王子
2
※ここでの『』の言葉は日本語です
再び視界が晴れた時、アルティウスがいたのは王宮の奥の神殿だった。
床に書かれた不思議な呪文の上に立っていたアルティウスの姿を見付けると、居並んだ臣下達は跪いて深々と頭を下げ
た。
秘密裏に事を運んだのだろう、いたのはアルティウスに命と忠誠を捧げた数人だけだ。
「ご無事でなによりです」
最初に口を開いたのは、アルティウスの片腕とも言うべき、将軍のベルークだ。
まだ30手前にして軍の最高司令官であるベルークは、アルティウスの妹姫の許婚であったが、前の戦で人質に取られた
妹姫は、陵辱された上殺された。
怒り狂ったベルークは相手国をほぼ壊滅的に攻め落としたが、今だその傷は癒えないままでいる。
この国でも数少ないアルティウスに意見が出来る豪胆な人物だが、さすがに今回の事は予想の範囲以外であったらしく、
顔色はまだ青ざめていた。
「ディーガ、ご苦労だった」
「王よ」
「お前の先読みの力、此度のことで信じることにした」
「王」
上機嫌なアルティウスに、ベルークは一歩進み出て言った。
「その者は?」
肌の色も顔立ちも、この国の者ではないと見るからに分かる。
異国から召還されたアルティウスが腕に抱く人間が、この国にとってどういう存在になるのか、ベルークの口調は自然と厳し
いものになっていた。
昔から言い伝えられている言葉が、その場にいる者たちの頭の中に浮かんだ。
「異国で拾った」
「王!」
「本当に存在するとは思わなかったな・・・・・《滅びを呼ぶ強星の主》」
「お分かりになられているのになぜっ?」
遥か昔、異国から星が堕ちてきた。
類稀な美貌と知能の持ち主を最初に掴んだ王は、短期間の間に周辺の国を傘下におさめ栄華を極めることになった。
その力の源が異国の者だと推察した諸外国は四方から攻め込み、その後数十年間戦火は収まらなかったという。
最上の存在として語られてきた異国の星の話は今も消えていない。
すでに昔話の世界とはなっているが、もしかしたらという思いは、国の権力者なら誰でも持っているだろう。
「異国の星が我が国にあると知られれば、周辺各国が攻め入ってくるかもしれません。ただちに元の異国に返すか、始末
をするのが賢明です」
そうでなくとも砂漠が多くを占めるこの世界で、この国の豊かな自然は垂涎の的だ。
異国の者の話が漏れれば、それを切っ掛けにして戦を仕掛けてくることも考えられた。
「ベルーク」
「は」
「私はそんなに弱い王か?」
「いえ、勇猛果敢な我がエクテシアの王、アルティウス様。貴方を弱いと思う国民は、この国には一人も存在しません」
「ならば問題ない」
「しかしっ」
「国の為に連れて来たわけではないのだ」
「ならば・・・・・」
「ただ欲しいと思っただけだ。よいか、この者の存在は他言無用だ。もしも諸外国に知れることになれば、その者だけでな
く一族家臣共々、嬲り殺しだ」
「はっ」
口にしたことは必ず実行するアルティウスの性格をよく知る家臣達は、この瞬間今見た事実を全て封印することを誓った。
アルティウスは軽く頷き、そのまま自室に戻ろうと歩き始めた。
「王、私が代わります」
ベルークだけは今だ納得いかない顔をしていたが、アルティウスの腕に抱かれた身体を引き取ろうと声を掛ける。
しかし、アルティウスは足を止めることはなく、更に抱きしめる腕に力を込めて神殿から立ち去った。