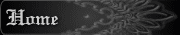正妃の条件
1
※ここでの『』の言葉は日本語です
シンプルで実用的なものを好むジャピオの部屋は必要最小限のものしかなく、アルティウスが腰掛けるイスも木で出来た
質素なものだった。
「足りないものは言わなければ分からぬぞ」
「王には十分なものを頂いております。わたくしには十分過ごし易い部屋ですわ」
「そうか」
それ以上なかなか話の進まない両親に、利発なエディエスが無邪気さを装って話し掛けた。
「父上が宮になかなかおこし頂けなくて、私も母も寂しい思いをいたしておりました。もっと頻繁にお会いしたいです」
それは暗にもっと母の元に通って欲しいと伝えたつもりだったが、直情的なアルティウスはそのままの意味に捉えたようだった。
「そなたは次期王となる身だ。遠慮などせず執務室に来ればよい。政など教えてやるぞ」
「・・・・・そうですね。でも、宮殿にはあの方がいらっしゃいますよね?私の母上はあの方に遠慮して、父上にお会いしに行
くことも出来ない」
「エディエスッ」
「それは誰のことだ」
アルティウスもその言葉の中に含む棘に気付き、少し眉を顰めて問い返した。
たとえ親子であっても王はこの国の中の一番の権力者で、逆らえばアルティウスは簡単に息子でも切り捨ててしまうだろう。
しかし、エディエスはどうしても我慢が出来なかった。
「父上はあの男に騙されているのです!確かに我が国民とは似つかない容姿ですが、それが異国の者だという証拠には
ならない!」
「エディエス」
「噂では、父上はあの男を正妃に迎えるとのこと!母上は世継ぎである私を生んだのですよっ?正妃は母上がなるのが
当然です!」
「お止めなさい!王っ、エディエスはまだ子供なのです!どうかこの暴言をお忘れくださいませ!」
「母上!」
とっさに跪き、額を床に付けるようにして謝罪する母親の姿を、エディエスは呆然と見る。
しかし、アルティウスは動じることなく口を開いた。
「よい、ジャピオ。エディエス、私はそなたの母を正妃にするつもりはない。私はユキを必ず正妃にするし、ユキ以外もう欲し
くはないのだ」
「父上・・・・・」
「ジャピオ、そなたはこの妾妃宮から出て行くことに異論をとなえるか?」
「いいえ、全ては王のお心のままに。わたくしは生家に戻らせていただきたいと思っております。ただ、心残りは息子エディエ
スのこと。まだ成人しておらぬ未熟な我が子を残して行くことだけが心配なのです」
「心配はいらぬ。エディエスは次期王として立派に教育を受けさせる」
「・・・・・」
あくまでも他人任せな言い方に、エディエスは俯いて唇を噛み締めた。
ジャピオの私室から出たアルティウスは、そこにリタとレスターの姿を見て苦い顔をした。
「レスター、お父様よ。きちんとご挨拶なさい」
「ご、ご機嫌、うるわしゅう、ございます」
9歳になるレスターは、リタの美貌を受け継いだ可憐な少年だった。
しかし、線の細い我が子をアルティウスはなかなか顧みようとはせず、リタ自身もレスターを身篭ってから今までアルティウス
の閨に呼ばれることはなかった。
美しい王とこの国の、両方を手に入れようと思ったリタの思惑は崩れ、若い肢体を持て余す日々が続いていたのだ。
そんな時、《星》の出現を噂で聞いた。
そして、王がその《星》を、それも男を正妃にすると通達してきた時、リタの憎悪は《星》ただ一人に向かった。
「王、今宵はごゆっくりと、わたくしの部屋で・・・・・」
「リタ」
「はい」
名前を呼ばれ、艶っぽい視線を向けてくるリタに、アルティウスはうんざりとした口調で言った。
「早々に退去する準備を整えよ。ただし、そなた1人でだ。レスターはこちらで養育する」
「王!」
信じられないというふうに綺麗に縁取られた目を大きく見開くリタだが、それが真実驚いているのかそれとも芝居なのか、
アルティウスにも見分けは付かなかった。
「わたくしとレスターを引き離すとおっしゃるのですかっ?可愛い我が子を置いて行ける母親などおりませぬ!」
「・・・・・そなたはレスターの養育を側仕えに任せ、夜は街に降りていると報告をうけているが」
「そ、それは、王がお召しになってくださらないから・・・・・っ」
「姦通は死罪だ」
「!」
「不問にふす代わり、黙って宮を立ち去るが良い。他の者にもおって命ずる」
「王!」
それ以上会話をするのも煩わしいと、アルティウスは踵を返す。
その時、一瞬レスターの顔が目に入ったが、レスターは父親を怯えたような目で見ているだけだ。
(せめてエディエスの半分でも活力があればよいものを・・・・・)
アルティウス自身、幼い頃から次期王として早々に母親から離されて教育されてきただけに、子供との接し方が分からな
かった。
早く一人前になって欲しいと思うが、可愛いとか愛おしいとか思う気持ちは抱けない。
アルティウスに人間的な感情を与えたのは、有希ただ1人だけだった。