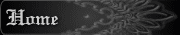正妃の条件
11
※ここでの『』の言葉は日本語です
リタの脱走をアルティウスから聞かされた有希は、一瞬頭の中が真っ白になってしまった。
軟禁されてからずっと、リタがアルティウスと有希に対して呪詛の言葉を吐き続けていたということは、直接聞かないまでも
噂は自然と耳に入ってきていた。
そんなリタが外に出て自由になった時、どんな行動をとるのか・・・・・。
「アルティウス・・・・・」
その不安が表情に出ていたのか、アルティウスは直ぐに手を伸ばして有希を抱きしめた。
何時もなら恥ずかしさと困惑で直ぐに身を捩る有希も、今は素直にアルティウスの腕の中に納まっている。
「心配せずともよい。そなたには一筋の傷さえ負わせぬ」
「・・・・・レスターには伝えた?」
「ああ。かなり動揺していたようだ」
「アルティウスが会ったの?」
「いや、ベルークだ」
「駄目じゃない!お父さんのアルティウスがちゃんと声を掛けてあげなくちゃ!」
「ユキ?」
あんなに母親のことを心配していたレスターが、その母親がいなくなったと知った時・・・・・自分だけがここに取り残されてし
まったと思った時、どんなに悲しく、苦しいか。
有希は自分まで苦しくなった。
「僕だけじゃなくて・・・・・レスターも抱き締めてあげて」
どんなに暴君でも、どんなに我がままでも、アルティウスの腕の中はこんなにも温かい。
有希は自分だけがそんな特権を持つことが心苦しかった。
「・・・・・分かった、後でレスターに会いに行こう」
「本当?」
「そなたに嘘は言わぬ」
「・・・・・そうだね、アルティウスは嘘は言わないね」
少し安心した。
「レスターの様子、後で教えて」
「分かった」
宮の中がざわめいている。
たかが女1人の逃走というわけではなく、リタの婀娜花のような存在感はかなりの影響があるようだ。
(こんなことで浮き足だつとは・・・・・)
有希を帰した後、アルティウスは険しい顔のまま、王宮の地下にある監獄にやってきた。
暗い石の壁に囲まれた幾つもの部屋の中には、これから刑が確定して流刑にされる者や、今から審議を受ける者など、
罪を犯した人間が何人もいる。
その一番奥の部屋に、政治犯だけが入れられる拷問部屋があった。
「王」
アルティウスが中に入ると、手に鞭を持ったベルークが振り返って跪いた。
「吐いたか」
「やはり、全ては知らぬようです。逃がした後、まだウロウロと妾妃宮の前をうろついていたくらいですから」
「・・・・・」
ベルークの報告を聞きながら、アルティウスは石壁に鎖で両手両足を繋がれた男を見た。
鞭で引き裂かれたその服は、衛兵の着ているものだ。
「イッダ」
「・・・・・」
「顔を上げよ」
「う・・・・・・ぁ・・・・・」
乾いた呻き声を上げながら、ゆっくりと顔を上げたのは妾妃宮の衛兵だったイッダだ。
まだ22歳のイッダは爽やかでスマートな青年で、妾妃達の間では人気があったようだが、今は目元は赤黒く腫れ、唇も切
れて、その姿はとても同一人物とは分からないくらいだ。
「お前の知っていることは全て話したのか」
その言葉に微かに首を振る。
「軟禁者の逃走に手を貸したのは重罪だが、それと共に王の妾妃と密通するは更なる大罪。お前は分かってリタと通じ
ておったのか」
「お・・・・・それ、ながら・・・・・リタさ・・・・・まは、な・・・・・かなか・・・・・王のおわた・・・・・りがな・・・・・いた、め、お寂しく、
わた・・・・・しなどと・・・・・」
「警護をしていて気付かなかったのか。あの女は夜な夜な街に出ては、行きづりの男と寝ておったのだ。寂しいわけではな
く、己の欲望のままにな」
「お・・・・・う」
「今頃は他の男の閨で、お前を笑っているだろう」
「・・・・・」
「ベルークもお前に期待をしていた。それを裏切ったのだ、罪は重い」
軟禁とはいえ、厳重に見張られていたはずのリタが脱走出来たのは、このイッダの協力があったからだった。
軟禁されて直ぐ、リタは扉の向こうに立つイッダを誘った。
アルティウスの不実を嘆き、寂しいのだと涙を零して訴えた。
妖艶な妾妃の白い乳房を強引に掴ませられた時、若いイッダの欲望は爆発して、王の妾妃と不義の関係を持ってしまっ
た。
それから他の衛兵の目を盗んで何度も身体を重ねたが、ある日リタはここから出てあなたと一緒になりたいと訴えたのだ。
その時には既にリタの身体と性技に溺れきっていたイッダは、計画を立てて昨夜それを実行した。
しかし、待ち合わせの場所にリタは現われず、途方にくれて宮に戻ってきたイッダを、他の衛兵が確保したのだ。
「お前から金を貰い、不義の時間を見て見ぬふりをしていた者達は既に流刑に処した。身の内にこんなに腐ったやからが
いたとは、私も考えを改めねばならぬが・・・・・イッダ、お前の罪は他の者よりも遥かに重い」
アルティウスの口からリタの裏切りを聞かされたイッダは、開かない目元から涙を流した。
王がこんなことで嘘を言うわけはなく、結果、自分は騙されたのだと気付いたからだ。
「どう償う」
「・・・・・死・・・・・をもっ・・・・・て・・・・・」
「明日正午」
「・・・・・御意・・・・・」
死を持ってしかアルティウスに償えないと思うイッダは、小さい声で、しかしきっぱりと言い切った。