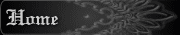正妃の条件
13
※ここでの『』の言葉は日本語です
13年前、当時16歳だったジャピオは、幼馴染のヒューティックと婚約をしていた。
当時まだ21歳の若さだったヒューティックは剣の名手で、アルティウスの父王が特別に目を掛けて異例の出世をさせたのだ。
13歳だったアルティウスの剣の師でもあったし、ジャピオと幼馴染だったことで、2人の事はアルティウスも承知のことで、似合
いの2人の結婚を嬉しく思っていたほどだった。
真面目で誠実、容姿も良かったヒューティックにはかなりの縁談の話があったのだが、幼い頃から想い合っていたジャピオし
か目に入れず、2人は周りから祝福されて結婚するはずだった・・・・・戦が起こるまでは。
数十年おきに起こってしまう戦。その時はエクテシア国とグランモア帝国に隣接する小国が戦を起こした。
小国ながらもかなり強い戦力で、2つの大国を相手にかなり押した展開になった。そこに、討伐軍として送られた精鋭の長
がヒューティックだった。
「まさか、あのような弱小国が、あれ程の抵抗をするとはな」
「・・・・・」
「ヒューティックの行方不明を、私も初めは信じられなかった」
山賊や罪人なども受け入れていたその小国の抵抗は凄まじく、討伐軍は相手の壊滅と引き換えにほぼ全滅という悲惨
な結果となってしまった。
まともな遺体などないという惨状の中、ただ1人、ヒューティックだけはその身体の一部分も見つからず、遺品さえなかった。
「生きていると思っているのか?」
「忘れるようにとおっしゃったのは王ですわ」
「・・・・・そなたを見ておられなかったのだ」
年上の美しく優しい幼馴染は、まるで生きた屍となっていた。ほとんど食事も取らず、笑わず、ただ生きているというだけの
存在になってしまった。
それをずっと見てきたアルティウスは、15の成人を迎えた時、ジャピオに自分の妾妃になるよう命じたのだ。
愛情は、確かにあった。しかし、それは家族に対するような情愛で、2人の間に肉欲といった生々しい感情は全くといってい
いほどなく、実際に身体を重ねた時も、まるでお互いを癒すという思いしかなかった。
アルティウスは子を産ませることでジャピオに生きる意味を与え、ジャピオはエディエスを生んだことによって生きなければと思
うようになった。
ただ、2人の心の奥底では、まるでしこりの様にヒューティックの存在が残っていた。
ヴェルニがイッダという偽名で仕官に上がってきた時、アルティウスは記憶に残るヒューティックの面影と重なるその姿に、直
ぐに内密に身辺を調べさせ、ヒューティックとのつながりを知ったのだ。
「わざわざ偽名まで使って仕官したのはそなたの為か?」
「・・・・・ヒューティックが行方不明になった時、あの子はまだ9歳の子供でした。私が妾妃として宮に上がったのは11歳、
あの子にとっては、私は兄を裏切った女に見えたのでしょう。名前を偽ってまで仕官した意味は分かりませんが、あの子は
本来素直で優しい子のはずです。リタ様との事は、確かに愚かで許しがたい過ちかもしれませんが、どうか、お慈悲を下さ
いませ」
「・・・・・私に、妾妃を寝取られた王と嘲笑されよと申すのか」
「そのようなことは・・・・・っ」
「兄の婚約者を奪った男の女を寝取る。その上、その男は王だ。ヴェルニにとっては、最高の復讐かもしれぬな」
「アル!」
思わず昔の呼び名を叫んだジャピオに、アルティウスは厳しい目を向けた。
「罪人はその罪を償わねばならぬ。それが王に対しての謀反ならば更に重い。ジャピオ、これは国の最高位に立つ者とし
てのけじめなのだ」
「・・・・・」
「処刑は決行する」
「・・・・・御意」
深く頭を下げたまま、ジャピオは顔を上げることが出来なかった。
「将軍!ベルーク将軍!」
アルティウスの執務室を飛び出した有希は、直ぐにベルークの姿を捜した。とにかく処刑を止める為に、何かしなければと
思った。
ベルークはちょうど地下に続くと聞いたことのある扉から出てきたところだった。
「ユキ様?」
ベルークは驚いたように足を止めた。
「いかがされた」
「処刑、止めたいんです!」
「処刑を?」
「アルティウスから、今日処刑をするって聞きました。どういう罪を犯したのか知らないけど、殺すなんて・・・・・っ」
「ユキ様」
ベルークは険しい表情のまま、有希にきっぱりと言った。
「その者は王に対して重い罪を犯したのです。処刑されるのは当然の処置」
「罪って?殺されるほどの罪って何ですかっ?」
「・・・・・リタ様の逃亡を手助けしました」
「リタのっ?」
「罪人の逃亡に手を貸すのは大罪です」
「そ、そうだけど、分かるけど・・・・・でも・・・・・」
「ユキ様、これは王の苦渋の選択なのです。お口を挟むことはお止め下さい」
「・・・・・」
「王に御意見出来るのは、ただ1人、正妃様だけなのですよ」
「・・・・・正妃・・・・・」
呆然と立ち尽くす有希に一礼して、ベルークは立ち去った。
残された有希は、今言われた事を何度も何度も頭の中で繰り返す。
(正妃だけ・・・・・そうなんだ・・・・・)
王に意見出来るのは、王と同等の立場、すなわち正妃だけなのだろう。
確かに今の有希の立場はまるで客と同じだ。幾らアルティウスに求婚されているとはいえ、正式に婚儀を挙げたわけでもな
い。
自分の躊躇いがこんな時に影響をするとは思ってもみなかった。
(王妃って、ただのお嫁さんってわけじゃなくて・・・・・)
政治的にも重要な位置にあるのだと、有希は初めて知った。
男同士だからとか、肉体を結ぶことが怖いとか、感情的なことしか目に見えていなかった有希にとって、今のベルークの言
葉は衝撃的で耳に痛かった。
もしも、有希がアルティウスと結婚していたら、今回の処刑は止めることが出来たかもしれないのだ。
「・・・・・っ」
王であるアルティウスと結婚するという本当の意味を悟り、有希は今にもグラつきそうになる足に力を入れて立っているの
が精一杯だった。