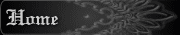正妃の条件
28
※ここでの『』の言葉は日本語です
「シエン王子が結婚するって、どうして教えてくれなかったの?」
「ユ、ユキ」
アルティウスは有希を抱きしめようと伸ばしかけた手を止め、まじまじと有希を見下ろす。
恨めしそうに上目遣いに見上げてくる有希はとても可愛らしいが、今のアルティウスにそんな暢気な感想を抱いている余裕は
無かった。
婚儀の警備の話し合いで遅くまで協議を重ねていたアルティウスは、今日一度も顔を見ることが出来なかった有希に会い
に、隣室に続く仕切り幕を開いた。
有希の部屋は今は王妃の部屋に換わり、アルティウスの私室と幕だけで仕切られている続き部屋で、何時でも王が自由
に出入り出来る構造になっている。
「ユキ」
「アルティウス」
始めはいきなり現われるアルティウスに慣れなかった有希も、今ではその存在を直ぐに受け入れられるほどには慣れてきた。
ただ、改めての初夜を迎えてから、アルティウスは最後まで有希を抱いてはいなった。
婚儀の準備などで時間が無いというのも本当なのだが、有希が全部自分のものになった安心感と、近々行う長丁場の婚
儀の為にも、出来るだけ有希の負担が増えないように、アルティウスは自分の欲望は抑えていた。
それでも、有希に触れたいという気持ちはやはり全て抑え込められず、毎日の口付けや、時折の有希にだけ快感を与え
る愛撫を施す為に、アルティウスは有希の部屋を訪れていたのだが・・・・・。
「・・・・・誰に聞いた?」
(有希に余計な話をしたのは・・・・・)
眉を顰めるアルティウスに、有希は溜め息をつきながら言った。
「誰でもいいでしょう?アルティウス、僕は怒ってるんだよ?こんな大事なことを、あなたではなくほかの人の口から聞いたこと
に。どうして言ってくれなかったの?」
「・・・・・有希があ奴のことを気に掛けるのが気に食わぬ」
「アルティウス」
「他国の王子の結婚などより、今は私との婚儀のことだけを考えれば良いではないか」
「あのね」
「煩いっ」
アルティウスはギュッと有希の身体を抱きしめた。
「今日やっとそなたと会えたというのに、なぜに他の男のことを話さねばならぬのだ!」
「・・・・・」
有希がシエンとこの国を出ようとしたことは、アルティウスにとっては今だに忘れられぬ出来事だ。あれ程深い絶望と怒りと嫉
妬を感じたことは無く、だからこそシエンの話題は僅かなりとも有希の耳には入れたくなかった。
有希がシエンのことを考えるだけで胸が煮えたぎるのだ。
痛いほど自分を抱きしめるアルティウスに、有希は息苦しさを感じながらも逃れようとはしない。
「アルティウス、僕は自分が幸せだからこそ、シエン王子にも幸せになって欲しいと思っているんだよ?」
「ユキ・・・・・」
ギュッと有希の方からも抱きしめ返され、アルティウスは少しだけ気分が落ち着いた。
「僕がす、好き・・・・・なのは・・・・・アルティウスだけなんだから・・・・・」
「!」
恥ずかしそうに言う有希の告白に、アルティウスは暴走しそうになる気持ちを抑えるのが精一杯だった。
そうでなくても何時でも有希を抱きたい、抱きしめたいと思っているアルティウスに、風呂上りのいい香りのする華奢な身体は
媚薬の役割にしかならないくらいなのだ。
何とか欲望を押し殺し、それでも有希を抱きしめたまま、アルティウスは渋々というふうに口を開いた。
「王子が婚儀を挙げるという報は確かに届いた。以前から決められていた許婚と、らしい」
「許婚・・・・・」
「ああ、それと、おかしなことも書いておったな。バリハンにも《強星》が現われたと」
「え?」
それは聞いていなかったのか、有希は目を丸く見開いて声を上げた。
「僕以外にも《強星》って呼ばれる人がいるのっ?」
「時間から考えれば、シエン王子が我が国から帰国して間もなくといったところだろうが、その者が真実《強星》かどうかは疑
わしい。今まで一時代に2つの《強星》が現われたことは一度も無いのだ」
「で、でも、わざわざ嘘をつくことは・・・・・」
「そなたが現われたことによって、諸外国はこれからも我が国が一段と巨大な国になると思っているからな。対抗する為に噂
だけでも流布する国が現われるやもとは思ってはいたが、まさかバリハンがとは・・・・・」
(あのシエン王子がそんな姑息なことをするとは思えないが・・・・・)
世に誉れ高き賢さを意味する名、青の王子を名乗るシエンがそんな愚かなことをするとはアルティウスも思ってもいないが、ど
の国にも馬鹿な臣下は存在する。
勝手に噂を振りまいているという可能性も無くはないのだ。
「嘘だって言うの?」
「祝いの使者の中に密偵を配した。近く結果はくるだろう」
「・・・・・どんな人なんだろう・・・・・」
「ユキ」
「ああ・・・・・僕、会ってみたいかも」
「許さぬっ」
「あっ」
突然、アルティウスは有希の口を塞いだ。もちろん自分の唇でだ。
「ん・・・・・っ」
有希の口から自分以外の者に対する思いを聞きたくなかった。
次の言葉を言わせないように、厚く長い舌で有希の口腔内を隅々まで嘗め回し、舌を絡めて激しく吸った。
「・・・・・っ」
アルティウスの肩に掴まっていた有希の指先が痛いほど肩に食い込んでも、アルティウスは簡単には口付けを解くことはしなかっ
た。
「・・・・っんぁっ」
やがて、まだ激しいキスに慣れていない有希は、アルティウスの舌技にたちまち陥落し、くったりと身体をもたれかけてくる。
その重みと身体の温かさに、アルティウスのペニスは当然の主張のように頭をもたげた。
「どうする、ユキ?私のこれは、ユキの中に入りたがっているようだが」
ワザとのように耳元で囁き、硬くなったペニスを有希の腰元に擦り付けると、有希の顔はたちまち真っ赤になった。
「ア、アルティウス・・・・・」
可哀想なほど震えている有希は、やはりまだ身体を重ねることに多少の恐怖感を抱いているのだろう。
婚儀も間近に迫っている今、アルティウスとしても有希に無理をさせることはしたくはなく、それでも大げさに溜め息をつきながら
少しだけ身体を離した。
「・・・・・今宵は、そなたの身体に触れさせてくれるか?」
「・・・・・触るだけで、いい?」
「婚儀まで今しばらくの我慢だ。それが済めば・・・・・毎日私をそなたに埋め込み、眠らせないぞ」
「じょ、冗談・・・・・だよね?」
「冗談だと思うか?」
夜のことだけは主導権は渡さぬと、アルティウスは傲慢に言い放った。