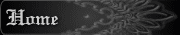正妃の条件
31
※ここでの『』の言葉は日本語です
階段自体が青白く光る石で出来ているようで真っ暗ではないのだが、感覚としてどこまでも下に下りているような気がした有
希は不安そうにカムラに言った。
「どこまで下に行くんですか?」
「もう、間もなくです・・・・・ほら、御覧なさい」
カムラの言葉通り、うっすらと輝く光が見えたかと思うと、そこに洞穴の入口のような場所が見える。
あの神殿の地下にこんな場所があるとは想像も出来ないものだった。
「こちらに」
「・・・・・」
有希はちらっとカムラに視線を向ける。無表情なその顔からは何も読み取れないが、あれ程アルティウスも信頼を寄せてい
るのだ、信じるしかなかった。
カムラに手を引かれて洞窟のような穴の中をくぐっていくと、やがて広く開けた場所に出た。
「わぁ・・・・・」
そこはまさに洞窟だった。
吹き抜けのように高くなっている天井も、壁も、地面も、全てが淡い光を放つ水晶で出来ていて、有希が周り中に映る自分
の姿を呆然と見つめていると、カムラは有希を促して奥の祭壇の前まで手を引いていった。
そこには・・・・・。
「・・・・・泉?」
「さよう。これが神水の源だと言われております。花嫁はこの神水に浸かり、世俗の汚れを洗い流すことを清浄の儀と申しま
す」
「でも・・・・・これ、深いですよね?」
そっと手を差し伸べて触れた水は思ったよりも冷たくは無かったが、湧き出るその底は真っ暗で見えない。
プールなどとは違い底が分からない泉に身を沈めるのはやはり躊躇いがあるので自然と声は震えてしまったが、カムラは祭壇
の前に供えられていた神体によく似た水晶を指差した。
「神の分身であるあれを手に取れば、溺れることはありません」
そう言われ、祭壇の方へ向けようとしていた有希の視線は、なぜかカムラの身体で遮られてしまった。
「カムラ?」
不思議そうに聞き返す有希に、カムラは静かに口を開いた。
「あなた様が現われなければ、この国の正妃はまた違ったお方がなられたことでしょう」
「え?」
「それは・・・・・リタでも良かったはずなのです」
「カ、カムラ?」
突然、どうしてカムラがそう言い出したのか全く分からなかったが、それでもどこか不穏な空気を感じて有希は泉から後ずさる。
「どう・・・・・して、リタのこと・・・・・」
「それはわたくしから答えましょうか?」
「!」
カムラとは別の声・・・・・それも聞き覚えのある声に有希は反射的に振り向く。
洞窟の入口には、あれ程手配してもなかなか尻尾を掴ませなかったリタが、嫣然と笑いながら立っていた。
「ど・・・・・して・・・・・」
神聖なはずのこの場所になぜリタが現われたのか、有希は一瞬幻がそこにいるのかと思った。
しかし、目の前に立っているリタは間違いなく本物で、目を見開くようにしている有希を嘲笑っている。
「お久し振りですこと、ユキ様。既に神への誓いは済まされたとか」
「・・・・・」
「ならばそこにいらっしゃるのは正式な正妃様というわけね」
豊かな髪は肩までの長さでばっさりと切り、商売女が着るような大胆に肌を露出させた服に、毒々しい化粧と、皮肉なことに
その装いはリタによく似合っていた。
「カムラ、あなたは・・・・・っ?」
「誰とて、我が子は可愛い」
「・・・・・我が・・・・・え?じゃあ、リタは・・・・・」
「神官に上がる前、まだ若かった私は、たった一度貴族の奥方と過ちを犯しました。まさかその一度で子が出来たとは思わ
なかった・・・・・」
「で、でも、どうしてカムラの子だと・・・・・」
この世界で科学的なことなど分かるはずが無いのに・・・・・。
「わたくしの父は子供が作れないのよ。母にも、両手で数えるほどの妾達にも、わたくし以外の子は出来なかった。王の妾妃
として王宮に上がる前に、母から聞いたのよ、本当の父の名を」
「リタ・・・・・」
苦しげにリタの名を呼ぶカムラに、有希は今の話が本当だということを悟った。
神と結婚し、ずっと独身を貫いてきた生真面目な神官長・・・・・彼にこんな過去の秘密があったとは、多分アルティウスも知ら
ないことだろう。
しかし・・・・・。
「リタ、僕もあなたに言いたいことがあるんだ」
「どんなご用件?」
馬鹿にしたような口調に出来るだけ乗せられないように、有希は一度大きく深呼吸してから言った。
「王宮を出る時にヴェル・・・・・イッダを利用したこと・・・・・彼があの後どうなったか知ってますか?」
「さあ。一時期の快楽の相手として、ああ、後は部屋から出る手段としてだけ存在していた男でしょう?その後どうなろうが
わたくしには関係のないこと」
「どうしてそんなふうに言えるんですか!彼はあなたを逃がした罰として、アルティウスに斬られて片目を失ったんですよ!」
「まあ・・・・・生きているの?」
「・・・・・え?」
「王のことだから、問答無用で討っておしまいになったかと思っていたけれど」
「・・・・・っ」
死んでいないことの方に驚いた・・・・・そう言うリタの顔に、悔恨や沈痛な表情は無い。
有希はこみ上げてくる感情を抑えるように、ギュッと拳を握り締めた。
「イッダに謝ってください!傷付けるような真似をしたことを謝ってください!」
「どうして?わたくしに何の罪があると言うの?」
「リタ!」
「王の妾妃に手を出せば、どんな罪になるかは分かっていたはず。わたくしの誘いに簡単に乗った愚かな男に、なんの謝罪が
いるという?むしろこのわたくしの肉体を好きに出来ただけ幸運だと思って欲しいわ」
「じゃあ、レスターのことはどう思うんですかっ?自分の子を悲しませて、それでも構わないと言うんですか!」
「レスターは王とわたくしを結ぶ存在。皇太子であったならば次期王の生母として力を得たものの、あの子はたった数ヶ月違
いとはいえ第二王子・・・・・本当に役立たずな子」
「・・・・・」
(駄目だ・・・・・この人には通じない・・・・・っ)
どんなに言葉を尽くしたとしても、元々の考え方が天と地ほども違うのだ。
有希は怒りを通り越して、リタを可哀相に思った。
有希はそんなリタから目を逸らし、じっと話を聞いていたであろうカムラを振り返った。
無表情だった顔に僅かながら苦悶の表情が浮かんでいる。
「カムラ、あなたはリタをこの場に引き入れて、僕をどうしようと思ってるんですか?」
「・・・・・あなた様のお命、頂戴したく思っております」
搾り出すようにカムラの口から漏れた言葉・・・・・それは有希が予想していた中の、最悪の言葉だった。