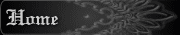正妃の条件
33
※ここでの『』の言葉は日本語です
突き飛ばされた有希が泉に落ちるのを見た瞬間、アルティウスは自分の心臓が止まるかと思うほどの衝撃を受けた。
そして、次の瞬間には、躊躇うこともなく有希の後を追って泉に飛び込んだ。
本来、国を守るべき王が自らの危険を考えないで行動することなど考えられないのだが、この瞬間はアルティウスの頭の中に
は有希の姿しかなかったのだ。
暗く、どこまでも深い水の中、目を凝らしていた視界の中に白い腕が見えた時、アルティウスは神に感謝し、もう離さないという
様に手を伸ばした。
「ユキ!ユキ!」
水の冷たさと、落とされたというショックで放心状態のようになっているものの、抱きしめる自分の身体に縋るように回された手
が、確かに有希が生きているのだと実感出来て、アルティウスは深い安堵の溜め息をついた。
「・・・・・」
アルティウスは有希を抱きしめたまま、打って変わった鋭い眼差しを2人の罪人に向ける。
アルティウスの突然の登場に目を見開いていたカムラは、やがてその驚きから立ち直ったのか、何時もと変わらぬ落ち着いた声
で言った。
「今時分、なぜここにおられる?明日の婚儀の直前まで聖木が見つからなければ、神の祝福がない結婚という烙印が押さ
れてしまいますぞ」
「神木を取りに行くのは婚儀の前日。その時刻までは定められておらぬからな。既に日付が変わった瞬間に出立した」
「しかし、それでもこの時間に・・・・・」
「カムラ、私の妃はまこと、《強星》だ。あのソリューがまるで空を飛ぶかのような速さで走り、神林に着けばその入口に神木は
あった」
それは、アルティウスにとっても不思議なことだった。
有希とカムラを2人きりにさせるのはやはり心配で、日付が変わると同時に宮を飛び出した。
一番足の速いソリューを用意させてはいたが、その速さは尋常ではなく、全く護衛も付いてくることが出来なかったくらいだ。
通常の半分ぐらいの時間で神林に着くと、目の前に広がっていたのは・・・・・。
「森全体が輝き、神木となっていた」
本来なら中に入って探さなければ見つからないであろう神木。しかし、その時は木々全てが輝く神木となっていた。
アルティウスは手の届くところにあった純白の花をつけた枝を一本手折るだけだったのだ。
最短の時間で戻ってくることが出来たアルティウスは、そのまま神殿に駆け込み、姿のない有希の姿を捜して・・・・・。
「リタの香油が香っていたからな。そのおかげでこの地下神殿に気付いた」
アルティウスは有希をベルークに預けて立ち上がると、濡れた髪をかき上げた。
「カムラ・・・・・そなたが私を裏切るとは思いもよらなかった」
「王・・・・・」
「私が幼き頃より既に神に仕え、先代の父と共に様々な神事を執り行なってきたそなたが・・・・・このような女の為に血迷っ
たのか!」
「・・・・・っ」
激しいアルティウスの言葉に、カムラはその場に膝を着いた。
「いかような責めもお受け致します。ただ・・・・・お情けを頂けるならば、どうかリタの命はお助けを」
「なぜにそのような女を庇う!」
「リタは・・・・・私の娘なのです」
身体を包む布ごとベルークに抱きとめられていた有希は、ぼんやりとその情景を見つめていた。
(やっぱりアルティウスも知らなかったんだ・・・・・)
カムラが自分とリタの関係を吐露した時、アルティウスの目は張り裂けんばかりに見開かれた。
信頼していた家臣の裏切りの要因がそんなところにあったとは、さすがに想像出来なかったのだろう。
「情けないっ。あなたには何の力もないのっ?」
2人の衛兵に腕を取られ、その周りも何人もの衛兵に囲まれていても、リタの気勢は衰えなかった。
跪くカムラを蔑むように見、その視線を有希に向けてくる。
「あのような得体の知れない者に、このエクテシアの王妃の座を与えても良いものかっ?」
「リタ!」
アルティウスが制しても、リタの口は止まらなかった。
「人々が欲しがるという《強星》は、同時に《滅びを呼ぶ者》でもあるはずだわ!そこにいる忌み人こそ捕らえて処分したらどう
なの!」
「・・・・・」
(僕が・・・・・滅びを・・・・・?)
確かに以前《強星》の説明を受けた時、そんなことを聞いた気がした。
善と悪、まるで表裏一体な存在だなと、まだ自覚がなかった頃の有希は客観的にそう思っていたくらいだ。
一瞬、目を伏せそうになった有希だったが・・・・・。
「私がそのような言い伝えに負けるとでも思っているのか!」
直ぐにリタの言葉を雄々しく打ち消す声に、有希はハッと顔を上げた。
「真実有希が《滅びを呼ぶ強星の主》だとしても、私がそれを全て凌駕してみせるわ!」
「アルティウス・・・・・」
粟立ちそうな心の中の不安を、直ぐに打ち消してくれるアルティウス。有希は何度も小さく頷いた。
(・・・・・うん、大丈夫・・・・・。僕には、アルティウスがいる・・・・・)
「カムラ、リタ、両名、我が正妃ユキを手に掛けようとした罪、かなりの重罪であるとこころえよ」
「・・・・・っ」
「・・・・・」
「その命を持ってしても償いきれるものではないが、このまま生かしておいても負にしかならぬ存在。婚儀が済み次第、処刑
を決行する」
「!ま、待って!」
処刑という言葉を聞き、有希は思わずそう叫んでしまった。
「ユキ、今回はヴェルニの時とは違う。こやつ等の罪は目を瞑る事は出来ぬ」
「うん、分かってる、分かってるよ、でも・・・・・」
有希は跪くカムラと、拘束されながらも顔を上げたままのリタを交互に見つめる。
「人が死ぬのを黙って見てるなんて・・・・・出来ない・・・・・」
綺麗事などは言わない。
実際、今泉に落とされ、死ぬかも知れない目に合わされたのだ。怒りはあるし、憎らしいとも思っている。
しかし、リタにこれ程の悪事をさせた要因には確かに自分の存在があった。この世界にはイレギュラーな存在の自分がいなけ
れば、リタの欲望も違った形になったかもしれない。
それに、カムラは長い間実子とは知らなかったリタに対する罪悪感でこの悪事に手を貸したのだろうし、それまでは実直にアル
ティウスに使えてきたはずだった。
「ユキ」
アルティウスが怒っているのは自分の為だという事もよく分かっている。
有希は両者にとっていい方法を考え、そして・・・・・ふと思いついてパッと笑みを浮かべた。
「アルティウス、明日は僕達の結婚式だよね?」
「・・・・・そうだが」
「おめでたい・・・・・事だよね?」
「何が言いたい?」
有希が何を言おうとしているのか、アルティウスは怪訝そうに聞き返してくる。
「僕の世界では何かおめでたい事があった時、恩赦っていって刑罰を軽くするシステムがあるんだ。だから、ええと、死刑にさ
れるような罪を犯している人でも、死刑は取りやめてそれより軽い罰を与えるっていう・・・・・」
たどたどしい説明だったが、有希が言いたいことは伝わったらしい。
アルティウスは腕を組み、深く考えるように目を閉じた。