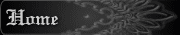正妃の条件
36
※ここでの『』の言葉は日本語です
長い祝宴が始まった。
上座に席を作られた有希は儀式の時とは正反対に、額や耳、首に腕輪と、豪奢ながらも上品な宝飾を身に纏った、まさに
王妃という格好で座っている。
(あんまりお金を使って欲しくなかったんだけど・・・・・)
アルティウスに無駄遣いを止めろという方が無茶なのかもしれないが、有希はこの身に着けている宝飾が一体いくらなのか、考
えるだけでも怖くなった。
「・・・・・」
隣にいるアルティウスはというと、次々と挨拶に来る各国の使者や国の重鎮達に酒を注がれながら上機嫌で笑っている。
もうどれくらい飲んだのか、自分でも分かっていないだろう。
「いや〜、アルティウス王が羨ましい!これほど美しい上に、《強星》であられる花嫁を娶られるとは!」
「まこと、エクテシアの繁栄は約束されたようなものですな!」
口々の賛美は真実思っているものか、それとも単に口先だけのものかは分からない。
それでも、アルティウスはどの言葉にも鷹揚に頷きながら杯を上げた。
「おお、我ほど幸せな者はおらぬ!」
「・・・・・」
(アルティウス、飲み過ぎだよ)
ずっとハラハラしていた有希は、客が途切れたのを見計らってアルティウスに言った。
「アルティウス、お酒飲み過ぎ。もう止めたら?」
「おお、ユキ、我が妃よ!」
アルティウスは不意に有希を抱きしめた。
「そなたを手に出来てどれ程嬉しいか分かるかっ?」
「ア、アルティウス、お客さんの前だよっ」
「構わぬ!世界で唯一の存在であるそなたが私のものだと、世界中の人間に知らしめたいのだ!」
「・・・・・もうっ、飲み過ぎだよっ」
非難するものの、有希は自分の顔が笑っているのを自覚していた。儀式が終わってホッとしたこともあるが、有希もアルティウ
スと結婚したことは嬉しいことなのだ。
これ程想われて、自分も大好きで、ずっと怒った顔をしろという方が無理だった。
「酔い潰れても知らないよ?」
「おお!今日はそれ程に酔えそうな気分だ!」
幼い頃から酒に慣れていたアルティウスは、ほとんどと言っていい程酒にのまれることはない。
それでも、今日だけは気分が高揚しており、何時もよりは何倍も心地よい気分を味わっていた。
その時・・・・・。
「王」
ベルークが側に来て、アルティウスの耳元で何事か囁いた。
すると、今まで上機嫌だったアルティウスの眉が僅かにひそまる。
「アルティウス?」
「ユキ、私は少し席を外すが、そなたはここにいろ。ベルーク、任せたぞ」
「はっ」
そのまますくっと立ち上がり、まるで一滴も酒など入っていないかのような足取りで広間から出るアルティウスの背を見送った有
希は、一体何があったのかとベルークを振り返った。
「将軍、何か・・・・・」
「王妃様には、何もご心痛されることはございませんよ」
「でも・・・・・」
「ほら、お次の御使者が。王の名代でご立派にご挨拶をなさいませ」
「あ、はい」
その言葉に、有希はそのまま意識をそちらに向けてしまった。
アルティウスは妾妃宮のジャピオの部屋に向かうと、声も掛けぬままいきなりドアを開けた。
「王」
こんな暴虐な行為も、この宮の主であるアルティウスならば許されることで、ジャピオも少し驚いたように目を見張ったが、直ぐ
に膝を折ってアルティウスに礼を取った。
「このたびはご成婚おめでとうございます」
「今宵宮を出るつもりと聞いたが・・・・・ユキには会わぬまま行くのか?」
「これからしばらくはユキ様もご多忙でございますから、わたくしの為にお時間を頂くつもりはありませんわ」
穏やかに笑う年上の幼馴染の真意を、愛情ではないが家族のように思っていたアルティウスには容易に想像が出来た。
「1人でグランモアに行くつもりか?」
「・・・・・っ」
「そなたのような女の一人旅など、途中で襲われ身を汚されて売り飛ばされるのが目に見える」
「アル・・・・・、わたくしは、どうしても自分の目で確かめたいのです、本当に・・・・・あの方は亡くなっているのか・・・・・今の
ままでは、自分だけ安穏と生きている感じがして・・・・・たまらなく辛いのです・・・・・」
「ジャピオ・・・・・」
13年前のあの時、あの戦からジャピオの時は少しも動いていなかったのだと、アルティウスは改めて感じて唇を噛み締めた。
先代の父王の頃の戦だが、アルティウスにとってもあれ程悲惨な戦は覚えが無い。
特に親しかったヒューティックが戦死とも行方不明とも分からない状態で、しばらくジャピオまで生きた屍のような生活を送って
きたということは消せない事実だった。
アルティウスも何度か《白の賢人》と言われるイムジン王が治めるグランモア帝国に照会をしたが、丁寧ながらも手掛かりは
ないという返事ばかりが返ってきた。
王となってからは単身で動くということがなかなか出来ず、何時の間にか記憶の片隅に押しやられた格好になってしまったが、
それは子を生したジャピオにとっても同じだったに違いない。
それが、今回ヒューティックの弟であるヴェルニの登場で、あの事件に再び焦点が当たったのだ。
ジャピオの再燃した想いは、とてもアルティウスの制止で止めることは出来ないものになっている様だった。
「行かせてくださいませ」
「ならぬ」
「アル!」
「しばし、時間が欲しい。私がよしとするまで、そなたはここにいてユキの後見人になって欲しい」
「わたくしが・・・・・ユキ様の?」
「この世界で、ユキが頼るものは私しかおらぬ。そのユキの助けになって欲しいのだ」
「・・・・・」
「よいか、ジャピオ。私もヒューティックは生きていると思いたい。その為に動くのだ、私を信じてくれ」
「・・・・・」
「それでも行くと言うのならば、そなたのその細い足に鎖をつけて繋いでしまうぞ」
冗談のように言うものの、それでもアルティウスならばやりそうなことに、ジャピオの頬に苦笑が浮かんだ。
「ユキ様はご苦労なさいますわね、王のような方を御するのですもの」
「ふんっ」
「・・・・・分かりましたわ。王のお言葉を信じ、しばらく待つことにします」
「・・・・・」
アルティウスはその言葉に深く頷いた。
近い内に、イムジン王と対さなければならないと思うと、浮かれ切っていた頭の中がピシリと引き締まる。
同じ年のシエン王子とは違い、自分の父親に近い歳の賢人に、どう切り込んでいくかを早々に考えなければならないだろう。
(それでも・・・・・私は負けることはない)
この世界の一番の王は自分だと、アルティウスは強く自分に言い聞かせた。