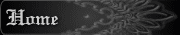正妃の条件
6
※ここでの『』の言葉は日本語です
有希は近くにあった平らな石の上にジャピオを座らせた。
この国の人間は一様に褐色の肌をしているが、ジャピオはどこか顔色が優れない様な気がしたからだ。
「体、あまり良くないですか?」
「お気遣い無く、ユキ様」
「・・・・・急に、会いたいと思って・・・・・ごめんなさい」
「いいえ、わたくしもお会いしたいと思っていましたわ。でも、王はなかなかお許しを下さらず、こうしてユキ様の方から訪ね
ていただけて、本当に嬉しく思います」
「ジャピオ様・・・・・」
「ジャピオとお呼び下さい。わたくしのような妾妃に敬称を付ける必要はありません」
少し話しただけでも、有希はジャピオがかなり知識の豊富な、頭のよい女性だということが分かった。
第一皇子を産んだことで、立場的には正妃に一番近い存在のはずなのに、慎み深いジャピオにその気は無いように感じら
れた。
「ユキ様、あなたがどういう思いでわたくしに会いたいと思ってくださったのかは分かりませんが、何も心配することはありませ
ん。王のお心は、ユキ様ただ1人に向けられておられます」
「でも、僕達、男同士・・・・・」
「性別など、真の愛の前ではささいな事に過ぎません。幸い、王には跡継ぎがおられます。お2人が結ばれることに何の
障害もありません」
結ばれる・・・・・改めて言われて、有希は赤面してしまった。
周りの空気で、有希は自分がアルティウスの伴侶となることを望まれていることは分かっていた。ジャピオの言うように、既に
子供のいるアルティウスに男の王妃がいても支障はないからだ。
しかし、有希自身はどうしても直ぐに首を縦に振ることが出来ない。
アルティウスのほぼ毎日のように繰り返される求婚の言葉も、素直に受け止められないのだ。
今、ジャピオにも言った通り、男同士だという理由も確かにある。有希の常識からはなかなか受け入れられないことだ。
ただ、それ以上に、有希には引っかかっていることがあった。
「ユキ様、王がお嫌いですか?」
「ううん!アルティウス、とても優しい。時々我がままで、怖いとこもあるけど、僕には優しい」
「それならば・・・・・」
「でも、アルティウスが好きなの・・・・・ほんとに僕かな」
「え?」
「僕が《強星》の主だから・・・・・《異国の星》だから、アルティウス、そう思ってるだけじゃないかな・・・・・」
杜沢有希という個人ではなく、たまたま欲しいと思っていた《強星》の主が有希だったから求婚してきているのではないか・・
・・・有希はどうしてもその不安が消せなかった。
「結婚したら、頼るのアルティウスだけ・・・・・それが怖い・・・・・」
「ユキ様」
「それに、男同士の・・・・・あ、あの時・・・・・」
「あの時?」
ジャピオは繰り返したが、有希の真っ赤になった横顔を見て、何を言っているのか直ぐに見当がついたようだった。
「王は乱暴でしたか?」
「う、受け入れるの、とても、怖い、です」
普段の有希なら、女性にそんなことなどとても言えるような性格ではなかった。
しかし、ジャピオが自分よりもだいぶ年上だということで、少しだけ甘えたくなったのだ。
ジャピオはそっと、目の前に立つ有希の手を握った。有希と同じくらいの大きさの手は、それでも柔らかく優しい。
「ユキ様が教えてさしあげて」
「僕・・・・・が?」
「王にとってのあの行為は、後継者をつくる為に行われていることが大前提なのです。まして、王は今まで誰かを愛おしい
と思われたことがない方ゆえ、どうしたらいいのかお解かりになっていないのでしょう」
「・・・・・」
「ユキ様が怖いと感じられたのは、それだけ王があなたに感情を向けたからでしょう。わたくしの時など、まるで仕事の延長
のように、感情など感じることはありませんでしたわ」
アルティウスとジャピオがそんな関係だと改めて聞かされると、やはり胸の奥がモヤモヤとしてしまう。
ただ、ジャピオに対しては、実際に話をしてみて印象はガラリと変わった。
皇太子の生母ということで、もっと傲慢な人間を想像していたが、こんなにも優しく機知に富んだ会話をする女性だとは嬉
しい誤算だった。
「会えて嬉しかった、ジャピオ。また会ってくれますか?」
「もちろんですわ。わたくしの知らない異国の話も聞かせて頂きたいし、それにお話したいことも・・・・・」
「何をしている!!」
突然浴びせられた罵声に、有希はビクッと身体を震わせた。
「エディエスッ、なんという言い方をするのですっ」
「母上!こやつに何かされませんでしたかっ?」
エディエスの恫喝はアルティウス譲りで容赦が無い。
有希は無意識に体が震えてきたが、このまま黙っていても変に誤解されるだけだと思い、思い切って振り向いた。
「こ、こんにちは、エディエス王子」
「こんなところで何をしている?ここは妾妃宮だ。王の許し無くして、王以外の男は出入りを禁じられている。それとも、男
であるそなたには女の慰めが必要か?」
「そっ・・・・・」
「無礼者!」
絶句している有希を背に庇うように立ちふさがったジャピオは、そのまま力任せにエディエスの頬を打った。
「母上!」
「そんな愚かで恥ずかしい言葉を言うそなたが息子だとは恥ずかしい・・・・・ユキ様、この子はまだ子供で、自分の言葉
の重大さを分かっておりません、どうぞお許しを・・・・・」
そのまま跪こうとするジャピオを慌てて押し止め、さすがにまだ強張っていたが有希は出来る限り笑おうとした。
「僕は大丈夫。ジャピオ、謝る必要ない」
「しかし、あんな酷い言葉を・・・・・」
「僕、少しだけ、分かる、エディエスの気持ち」
「そなたに私の何が分かる!」
既に喧嘩腰のエディエスは、まるで同情されているような気がしてギュッと拳を握り締めた。